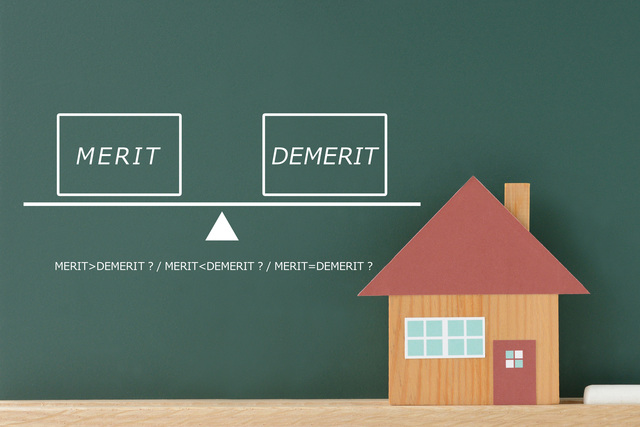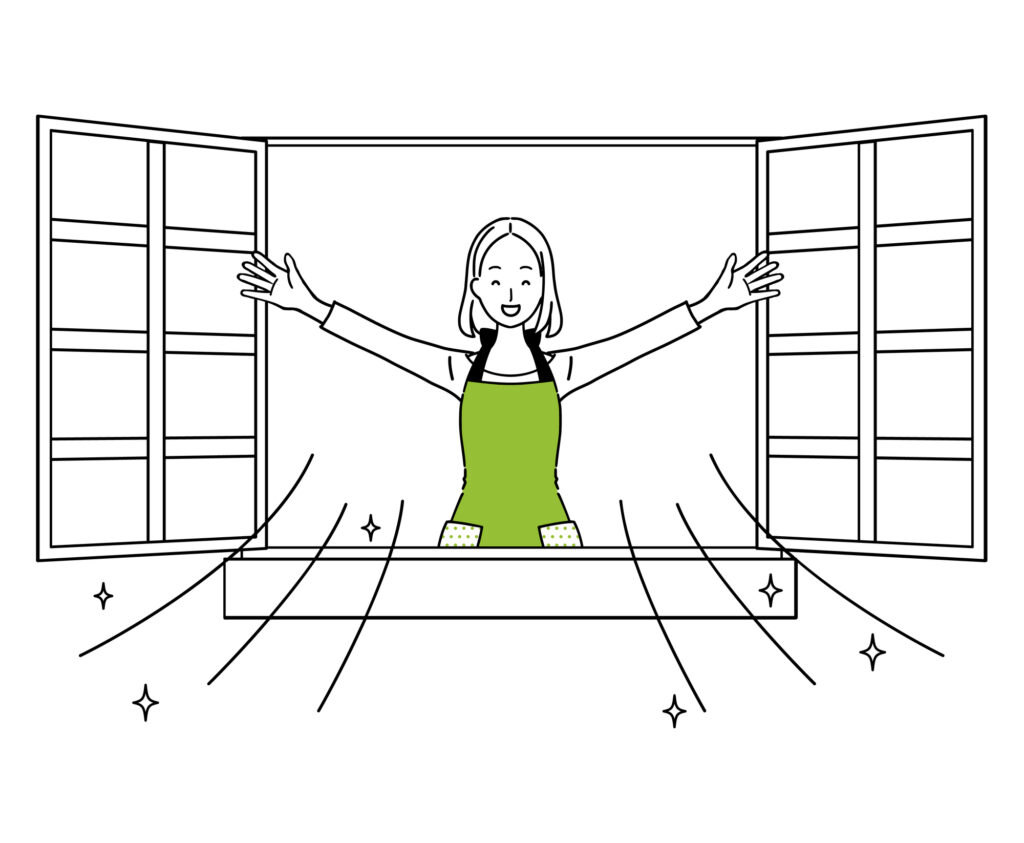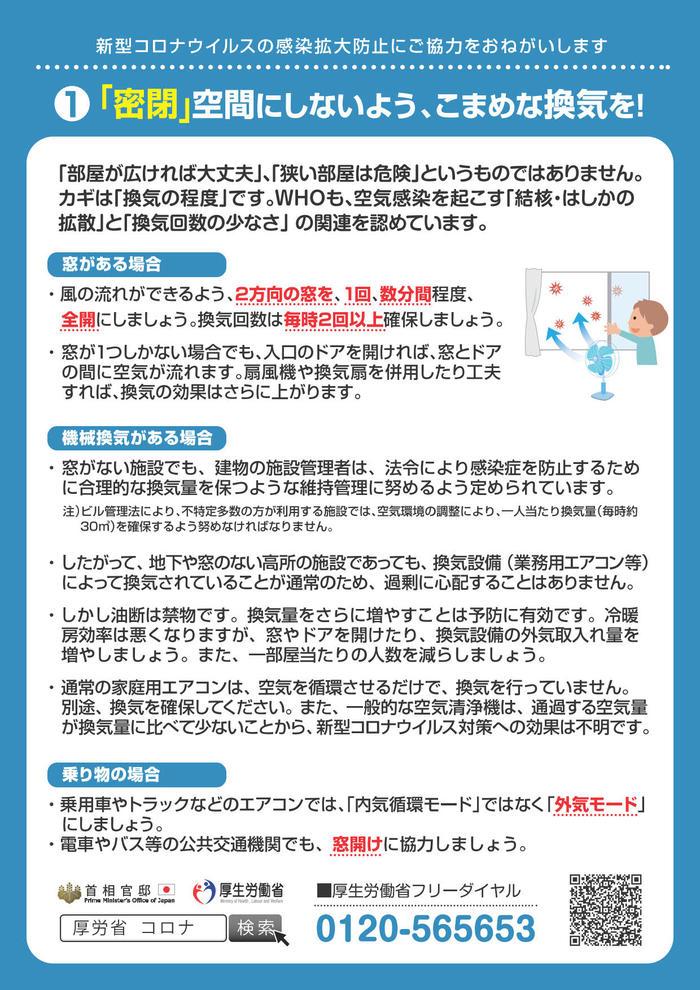窓の内側にシャッターを設置するとき、このような悩みはありませんか?
「窓の内側にシャッターを設置するメリットやデメリットは?」
「窓の内側に設置できる具体的な商品が知りたい」
シャッターといえば、窓ガラスの外側に設置するイメージを持っている方が多いと思いますが、実は窓ガラスの内側に設置するシャッターも存在するのです。
マンションの規約でシャッターの設置が禁止されている、戸建て住宅だけど屋外にシャッターの設置スペースがないなどの理由でシャッターの設置を諦めている方も多いですが、室内シャッターであれば設置することができます。
本記事では、窓の内側にシャッターを設置するメリット・デメリット、おすすめの商品について詳しく解説します。
福岡県内対応!窓シャッターはドアードで無料見積から!施工実績豊富で綺麗に安く工事可能!
窓の内側にシャッターを設置するメリット
窓の内側にシャッターを設置するメリットは以下の通りです。
- 防犯性に優れている
- 遮音性に優れている
- 雨の日でも開閉がしやすい
- 防寒対策に高い効果を発揮する
- 採光や通風を調節できる
- シャッターに汚れが付きにくい
それぞれのメリットについて、以下で詳しく解説します。
1.防犯性に優れている
窓の内側にシャッターを設置することで、防犯対策に非常に効果的です。
最近の窓ガラスは防犯性に優れていますが、シャッターを設置することでさらに防犯性を高めることができます。
防犯対策に効果的なシャッターには、防犯性能の高い建物部品を証明する「CPマーク」が付いていますので、購入するときにチェックするといいでしょう。
2.遮音性に優れている
室内にシャッターを設置することで、外からの騒音をシャットダウンすることができます。
なかでも、窓から道路が近い場合や、住宅同士が近い場合には大きな効果を実感できるでしょう。
また、室内にシャッターを設置することで、強風に煽られたときや強い雨が当たっているときに騒音となる金属音がしないことも大きなメリットです。
さらに、シャッターは遮光性にも優れているため、車のヘッドライトが直接当たる窓や明かりが気になる場所に設置することもおすすめです。
3.雨の日でも開閉がしやすい
窓の外に設置してあるシャッターを閉めるためには窓を開ける必要がありますが、室内のシャッターは窓を閉めた状態でも開閉できるため、シャッター開閉時に雨に濡れたり、室内に雨が侵入する心配はありません。
4.防寒対策に高い効果を発揮する
シャッターは遮熱性や断熱性にも優れているため、防寒対策にも期待ができます。
ただし、シャッターに直接太陽光が当たるため、夏場にはシャッターの温度が上がることに注意しましょう。
5.採光や通風を調節できる
室内に設置できるシャターは、ブラインドカーテンのように採光や通風がしやすいタイプもあります。
そのため、完全に太陽光や風を遮断したくないという方にもおすすめです。
6.シャッターに汚れが付きにくい
シャッターを室内に設置することで、雨風などによって汚れることがないため、お手入れしやすいという特徴があります。
シャッターは窓ガラスに比べて汚れが落としにくいですが、室内シャッターは汚れがつくことはありません。
窓の内側にシャッターを設置するデメリット

窓の内側にシャッターを設置するデメリットは以下の通りです。
- 窓ガラスを保護することができない
- 室内を圧迫する恐れがある
- 種類が少ない
- 値段が高い
- 窓ガラスの結露発生を防ぐことはできない
それぞれのデメリットについて、以下で詳しく解説します。
1.窓ガラスを保護することができない
室外に設置するシャッターは窓ガラスを保護する効果もありますが、室内にシャッターを設置してしまうと窓ガラスを保護することができません。
台風などによって窓ガラスが割れたとき、室内に散乱する心配はありませんが、窓ガラス自体は守ることができないことを覚えておきましょう。
2.室内を圧迫する恐れがある
シャッターを室内に設置することで、室内が圧迫される可能性があります。
室内にシャッターを設置する場合は、設置するシャッターのサイズやカラーなどを慎重に選ぶ必要があります。
3.種類が少ない
室内に設置するシャッターは、一般的な室外シャッターに比べると種類がかなり限られてしまいます。
機能性の高い室内シャッターもありますが、選択肢はそれほど多くないということを覚えておきましょう。
4.値段が高い
室外シャッターに比べると室内シャッターは価格が高い傾向にあります。
また、シャッター本体価格だけではなく、設置工事費用も高くなることがあるため、設置までの総額で費用を計算するようにしましょう。
5.窓ガラスの結露発生を防ぐことはできない
窓の外にシャッターを設置することで断熱性が高まって窓ガラスに結露が発生しにくくなりますが、室内のシャッターには結露発生を防ぐ機能はありません。
そのため、室内シャッターを締め切る時間が多い場合は窓ガラスとシャッターの間に結露が発生してカビが生えないように注意する必要があります。
窓の内側に設置できるおすすめのシャッター

窓の内側に設置できるおすすめのシャッターは以下の通りです。
- 文化シャッター 「マドマスタールーマ」
- 不二サッシ「セフティルーバー」
それぞれの商品について、以下で詳しく解説します。
1.文化シャッター 「マドマスタールーマ」
文化シャッターが販売するマドマスタールーマは、シャッターを設置できない住宅でも設置できるように開発されたシャッターです。
デザイン性にも優れているため、シャッターそのものがインテリアとして活躍することもできます。
リビング窓のような大きな窓だけではなく、勝手口などの小さな部分にも設置できるため、防犯面で不安な部分に設置することもおすすめです。
2.不二サッシ「セフティルーバー」
不二サッシが販売するセフティルーバーは、ルーバーの開閉により、通風・採光・外からの視線を自由自在にコントロールすることのできる室内シャッターです。
採光・通風などを調整できることはもちろん、二重ロック仕様となっているため防犯性が高いことも特徴となっています。
ニューホワイトとステンカラーの2色展開となっているため、お部屋の雰囲気に合わせやすいことも嬉しいポイントです。
まとめ
本記事では、窓の内側にシャッターを設置するメリット・デメリット、おすすめの商品について詳しく解説しました。
窓の内側にシャッターを設置することには、大きなメリットがある一方でデメリットも存在するため、総合的に判断した上で設置を検討したい部分です。
とはいえ、そもそも屋外にシャッターを設置できない住宅においてはメリットしかないため、検討してみることがおすすめです。
ぜひ本記事を参考にして、窓の内側に設置するシャッターについてチェックしてみてください。